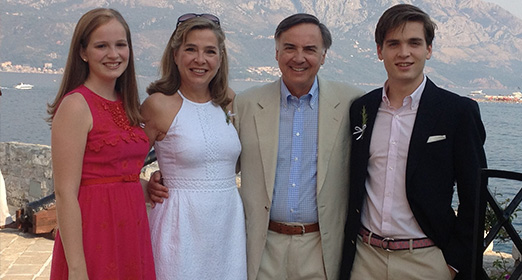9年前、デビッド・ショーとコリ・ショー夫妻は、3歳の娘キーガンと1歳の息子カーターを連れてパロアルトに引っ越しました。引っ越しに伴う通常の変化(父親の新しい仕事、娘の新しい幼稚園、新しい友達作り)に加えて、もう一つ乗り越えなければならない課題がありました。
キーガンとカーターは二人とも重度のピーナッツアレルギーと診断されており、カーターは牛乳、卵、木の実にもアレルギーがありました。一家は子供たちのアレルギーを理解し、安全を守るため、複数のアレルギー専門医に相談しました。
厳重に回避するようにと彼らは言われていたが、危険は常に存在していた。
スタンフォード大学フットボールチームの新しい攻撃コーディネーターにデイビッドが就任した頃、コーリーはキーガンとカーターを引き連れてスタジアムに到着すると、彼らの足元にピーナッツが転がっているのに気づきました。ある試合中、観客がピーナッツを投げつけており、その粉塵だけでもカーターはアレルギー反応を起こしてしまいました。
コリ氏によると、これは10年も経っていない頃のことだったが、当時はまだ食物アレルギーは一般の人々の意識に浸透しておらず、単なる厄介者、あるいはもっとひどいことに、過保護な親の空想の産物と誤解されることが多かった。こうした致命的なアレルギーに苦しむ家族は、しばしば孤立感を抱いていた。
ある日、キーガンの幼稚園で、コリは別の女の子の名札に気づきました。「テッサ」と書かれており、その下に「アレルギー:牛乳、小麦、卵、ナッツ、甲殻類」と書かれていました。コリはテッサの母親、キム・イェーツ・グロッソを探し出して会い、二人は危険な食物アレルギーを抱えながら生きてきたそれぞれの家族の経験、不安、そして希望を共有し、すぐに親しくなりました。
「文字通り、どうやって生きていくか考えていたんです」とコリは説明する。「食物アレルギーを持つ別の家族と知り合ったことで、世界が変わりました。スーパーマーケットを歩きながら、子供たちに安全な食べ物を探していた時のことを覚えています。キムが電話で、6番通路に行ってこのパンを買ってきて、などと丁寧に教えてくれたんです。私は安堵のあまり泣いてしまったんです。」
数年後、キムはスタンフォード大学の免疫学者カリ・ナドー医学博士と出会った。 (「食べられる」を参照)テッサが出会った中で、初めて彼女の多重アレルギーを治療しようとしてくれた医師は彼だった。しかし、食物アレルギー研究への資金不足が、研究を進める上で大きな障害となっていた。
「ナドー医師が臨床試験を実施し、特に多重アレルギーを持つ子どもたちの患者をこれらの致命的なアレルギーに対して脱感作することが可能であると証明するためには、資金集めが必要なのは明らかでした」とコリ氏は指摘する。
キム、コーリー、そして他の数人の母親たちが団結し、家族を巻き込み、コミュニティを築き、イベントを開催し、食物アレルギーへの意識を高め、臨床試験のための資金を調達し始めました。彼女たちの草の根の活動は小さな規模で始まりましたが、食物アレルギーという新たな流行に直面する多くの家族が協力し、研究に個人的な慈善支援を提供するようになるにつれて、活動は拡大していきました。
ショー一家がパロアルトに引っ越してから5年後、8歳のキーガン君と6歳のカーター君は、ナドー博士による経口免疫療法の臨床試験(ゾレアという薬剤を用いた)を受ける最初のコホートに加わりました。この試験は、複数のアレルゲンに対する脱感作を目的としたものでした。ナドー博士チームの監督の下、2年間にわたり、キーガン君とカーター君は慎重に計量されたアレルゲンを摂取し、徐々に用量を増やしていきました。そして最終的に、偶発的な曝露や交差汚染を恐れる必要のないレベルまで脱感作が進みました。
その結果は家族全員の人生を変えるものでした。
「彼女は私たちの家族、そして私たちの力関係そのものを変えてくれました」とコーリーは言います。「私たちはストレスを感じていません。日曜日には自転車に乗ってダウンタウンへ行き、レストランで夕食を食べました。彼女は私たちに普通の家庭生活を与えてくれました。」
言葉を広める
一方、ナドーの研究が成功したという知らせは、心配する別の親、女優のナンシー・カレルとスティーブ・カレルにも届いた。彼らの娘アニーは重度の乳製品アレルギーを患っていた。
アニーが言うように、食物アレルギーを持つことは「箱の中で暮らしているようなもの」でした。家の外で遊ぶことも、お泊まり会をすることもできず、レストランでの食事は不安で仕方がありませんでした。家族で旅行に行くときは、クーラーボックスに食べ物をぎっしり詰め込んでいました。「ホテルに着くたびに、まるでテールゲートパーティーをしているみたいでした!」とナンシーは回想します。
「カリが他の子の乳製品への過敏症を軽減することに成功したという記事を読んだ瞬間、『私たちも参加したい!』と思いました」とナンシーは言います。「アニーは8歳で、クラスメイトと違うと感じるのが嫌でした。彼女が一生この症状と付き合わなくて済む可能性があるなんて、信じられませんでした。」
アニーがスタンフォード大学で臨床試験を始めた頃、カレル夫妻の希望は控えめでした。「私たちの夢は、彼女が乳製品に偶然触れても深刻な後遺症にならずに済むことでした」とナンシーは言います。「『彼女がピザを食べられるといいな』とは思っていませんでした。『もしかしたら、ピザを食べたばかりの人と手をつないでいられるかもしれない』と考えていたんです。」
経口免疫療法は不安がつきものだった。「ロサンゼルスとの間を往復しながら、アニーには『体に毒だから食べないように言っていた食べ物、覚えてる?今から食べてほしい』と言い続けていました」とナンシーは言う。「最初から順調だったと言えば嘘になります。アニーは大変な苦労をしました。私たちは彼女の人生に敬意を抱いています。」
カレル夫妻がすぐに注目し、また乗り越えることができたのは、ナドー氏の思いやりと研究チーム全体のサポートでした。
「カリは優しい天才と呼んでいます」とナンシーは言います。「(自宅ではアレルギー反応が出る可能性のある)治験中は、彼女に何度も電話をかけました。彼女は毎回電話に出てくれて、すべてが落ち着くまでずっと私たちと一緒に電話をしてくれました。私は彼女を心から信頼しています。」
アニーが治験を無事に終えた後、カレル夫妻は食物アレルギーに苦しむ他の家族にも同じ機会を与えたいと考えました。彼らはナドー博士の研究を支援し、食物アレルギーへの意識を高める活動に積極的に取り組んできました。2011年には、スティーブは募金ガラの司会をボランティアで引き受け、友人で俳優仲間のダナ・カービーを招き、スタンフォード大学における食物アレルギー研究への支援を呼びかけました。また、スティーブは1時間のドキュメンタリーのナレーションを務め、意識向上のための公共広告にも参加しています。
「食物アレルギーを抱えて生きるのは非常に困難ですが、前向きに、そして積極的に取り組むべきです」とスティーブは言います。「食物アレルギーの根治的治療法の開発は日々進んでいるので、アレルギー研究を支援することは重要です。希望はあります。」
早期の提唱
22歳のステファン・ライノヴィッチさんは、スタンフォード大学でナドー博士が行った臨床試験に参加した最初のニューヨーク出身者でした。ステファンが幼児だった頃、医師は乳製品と卵に「重度のアレルギー」があると診断しました。外食や加工食品は絶対に避けるべきでした。卵や乳製品と同じ調理器具で調理された食品は、致命的なアナフィラキシー反応を引き起こす可能性がありました。食物アレルギーを持つ他の親たちと同様に、母親のレベッカさんは息子が口に入れるものすべてを注意深く観察していました。
ステファンの両親はもう一つの重要な措置を講じました。幼いころから彼が自らの権利を主張することを奨励したのです。
「息子がまだ幼い頃から、自分の意見をはっきりと主張し、真剣に受け止めてもらえるように力づけたいと思っていました」とレベッカは説明する。「私たちがいつも息子のために声を上げているわけにはいかないのは分かっていました。親としては、あっという間に小学校へ、そして高校、大学へと進学していくのですから。」
ステファンは2歳か3歳の頃から、自分の意思で話せる時はいつでもそうしていました。家族でレストランに行くと、自分で料理を持ってきたので「メニューはいらないよ、ありがとう」と説明するのがステファンの仕事でした。
ステファンは幼稚園に通う頃から、ウエストバッグにエピペンと計量済みのベナドリルを携帯していました。家族や学校の職員は常に予備を用意していましたが、両親はステファンに、自分の責任は自分で負う、自分の運命は自分で決めるのだということを教え込みました。この責任感は、食物アレルギーを持つ多くの子供が薬を持ち歩かない危険な時期である10代の頃に大いに役立ち、少なくとも一度は命を救ってくれました。
ステファンが食物アレルギーの臨床試験を受ける資格を得たのは、19歳になってからでした。当時、彼はマサチューセッツ州のウィリアムズ大学に在籍していましたが、臨床試験はアメリカ本土のスタンフォード大学で行われていました。これは一見、受け入れ難い状況でした。しかし、レベッカが「ナドー氏の機知に富んだ、そしてやり遂げる姿勢」と呼ぶおかげで、二人はすぐにユニークな解決策を見つけました。ステファンは臨床試験を受けながらスタンフォード大学の授業を受講し、ウィリアムズ大学に編入できる単位を取得できるのです。
その後の13ヶ月間、ステファンはスタンフォード大学に住み、パロアルトで授業に出席し、パートタイムで働きました。レベッカは毎月通院していましたが、治験の現実として、ステファンは「増量」の診察(研究チームがアレルゲンの投与量を増やす)に出席し、毎日自宅で処方された量の牛乳を摂取し、アレルギー反応から身を守るという責任を個別に負っていました。
しかし、多くの点で、ステファンはその経験を一人で経験したわけではありません。
「子どもを育てるには村全体の協力が必要だと言われますが、食物アレルギーのコミュニティではそれが最も真実です」とレベッカは指摘します。
カリ・ナドーさんから、同じ親であるキム・イェーツ・グロッソさん、医師助手のティナ・ドミンゲスさんまで、皆がサポートと友情、そして見守りの目を差し伸べ、ステファンさんが試験を無事に完了できるよう尽力してくれました。
それ以来、ライノヴィッチ夫妻はこれまで以上に食物アレルギーコミュニティに尽力してきました。レベッカは食物アレルギー研究教育(FARE)の理事を務め、夫のサシャと共に、ナドーの画期的な研究を支え、さらに発展させるために、戦略的な慈善寄付を行ってきました。
ステファンは啓発活動にも参加しているが、食物アレルギーが自分の特徴ではないと語る。現在はニューヨークの投資銀行センタービュー・パートナーズで勤務し、週7日勤務で毎日外食も厭わない、過酷なキャリアを歩んでいる。
未来は明るい
現在、全米各地からナドーの臨床試験に患者が参加しています。シカゴ出身の高校3年生、マシュー・フレンドさんは、その一人であることを誇りに思っています。
マシューは生後8ヶ月の時に小麦、大麦、ライ麦、オート麦に対する命に関わるアレルギーが発覚しました。ガーバーのマルチグレイン・ベビーシリアルを初めて口にした直後、全身にじんましんが出ました。最も避けるのが難しかったのは小麦で、両親はすぐに小麦が文字通りどこにでも使われていることを知りました。ルートビア、プリングルス、ブラウニー、ハンドクリーム、シャンプー、日焼け止めにまで小麦が含まれていたのです。マシューが高校に入学する頃には、家族の懸命な努力にもかかわらず、少なくとも10回は救急外来を受診していました。
「ナドー先生の診察は、我が子にとって14年ぶりの希望の光でした」と、マシュー君の母親、リンダ・レビンソン・フレンドさんは言います。「他の医師からはエピネフリンを服用し、小麦を避けるように指示されていましたが、ナドー先生はマシュー君が充実した普通の生活を送れるよう、進んで準備を整えてくれました。」
マシューが2012年8月に治験を開始した当時、彼のアレルゲンはごく微量でもアナフィラキシーを引き起こす可能性がありました。治験開始から8週間後、ナドー医師は彼に「交差汚染を受けなさい」と指示し、マシューは曝露にうまく耐えることができました。治験終了時には、彼は毎日カップケーキ1個、オレオ6個、小麦を含むグラハムクラッカー1枚、オート麦を含むグラノーラバー1本、ライ麦粉と大麦粉で作られたクッキー4枚を食べていました。彼は、以前は致命的だったアレルゲンに対する脱感作を維持するために、今も毎日これを続けています。
「ナドー先生と素晴らしいスタッフの方々には、本当に感謝しています」とリンダは言います。「マシューのように複数の食物アレルギーを持つ子どもたちに脱感作療法を施し、素晴らしい成果が出ています。このプロセスに携われるのは、非現実的で素晴らしい経験です。」
マシューの家族が社会貢献の方法を探し始めた時、シカゴの地元ネットワークに連絡を取り、スタンフォード大学の研究を支援することが全国的な影響を与えることを友人や同僚に説得しました。今日、リンダと夫のビル、そして彼らが動員した他の寄付者のおかげで、臨床試験はシカゴ、ニューヨーク、ロサンゼルスに開設され、より多くの家族が地元で人生を変えるような研究に参加できるようになりました。
マシューにとって、この裁判は非常に重要な変化をもたらし、彼は ハフィントンポストのブログ 食物アレルギー研究における「人間実験台」としての経験を語り、自身の経験を語り、命に関わる可能性のある食物アレルギーを持つ他の10代の若者たちに、普通の生活を送る希望があることを知ってほしいと願っています。マシューはまた、今でもエピペンを2本持ち歩いていることをすぐに指摘します。彼は減感作療法を受けており、交差汚染から保護されていますが、治療はまだ実験段階であり、アレルギー反応が出る可能性があるからです。
「機会があればいつでも、他のご家族とお話ししたり、ご案内したりさせていただきます」とマシューは書いています。「カリ・ナドー博士とそのチームがスタンフォード大学、そして今では全米各地で行っている革新的で素晴らしい研究のおかげで、食物アレルギーを持つ人々は充実した人生を送ることができるようになりました。私は、食物アレルギーを持つ人々の未来が非常に明るいことを実証しています。」
この記事は2015年春号に掲載されました。 ルシール・パッカード 子ども向けニュース.